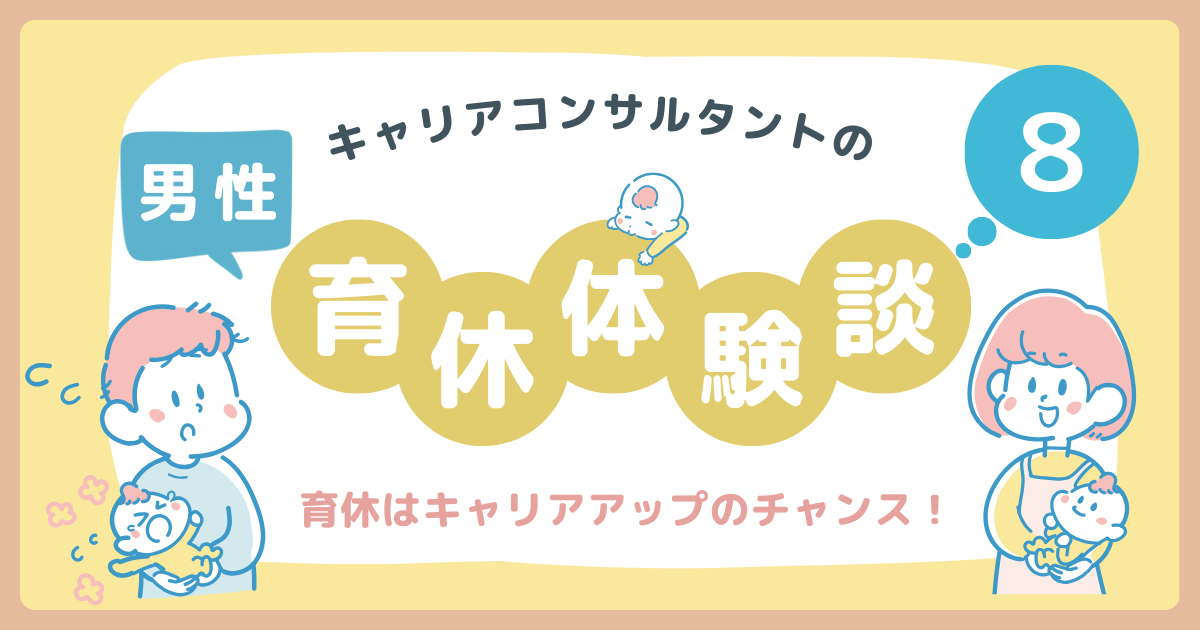前回の記事では、育休開始前の前半(妊娠初期・中期)の家庭生活についてご紹介しました。
今回は、育休開始前の後半(妊娠後期)についてご紹介します。
共働き家庭の妊娠後期の家庭生活
家事・育児分担の変化
妻のお腹がだいぶ大きくなり、屈むことがほぼできなくなってきたので、屈む作業を伴う掃除(お風呂掃除など)を夫である私の役割にしました。
長女の保育園送迎は、基本的には引き続き妻が行い、都合がつかない場合は私が送迎していました。
自転車での送迎のため、お腹が大きくなってからはバランスを崩しやすいのではと少々心配していましたが、妻曰く、イヤイヤ期の子供を歩いて送迎するよりは自転車の方が断然楽とのことでした(笑)
育児で分担を変えたのは長女のお風呂。
それまで長女のお風呂は、本人の希望で妻と入るか私と入るか決めていましたが、後期はなるべく私が入れるようにしました。
妻はお腹の張りを感じやすいようで長湯はしない方が好ましい状況でしたが、長女がいるとどうしても長湯になります。
また、浴槽の出入りの際、長女を抱き上げる必要があり転倒のリスクも伴います。
上記のように、全体的に私の家事育児分担が増えましたが、極力仕事を定時に帰れるように業務調整し、分担が増えた家事・育児もほぼ問題なく(?!)こなせていたと思っています。
妻の勤務体系は変化なし
コロナ禍を経た2024年の執筆時現在、オフィスワークは在宅勤務可能な職場も増えていますが、2017年当時は世の中的に在宅勤務はほぼ存在しない状況でした。
妻もまた、2017年当時は毎日出勤が必須でした。
妊娠後期になると、お腹が張りやすく長時間立ち続けない方がよい状況ではありましたが、オフィスワークで座り仕事だったこともあり、また、長女の育児で時短勤務をしていたこともあり、妊娠前と変わらぬ勤務体系(時短勤務で毎日出勤)を継続できていました。
通勤時も、30分以内で、時短勤務でラッシュのピークからズレた時間だったので、特に問題なく通勤できていたようです。
アクシデント発生、妻が切迫早産に
第一子妊娠時同様、第二子も切迫早産に
前回の記事でもお伝えしましたが、妻の入院先の産婦人科医の話によると、第一子で切迫早産になった場合、第二子も切迫早産になる可能性が高いとのことでした。
安定期を過ぎてからしばらくは、特に大きなアクシデントもなく、無事に過ごしていましたが、やはり妻の産休まで残り1か月というタイミングで、切迫早産になってしまいました。
出産予定日、つまり夫の私の育休開始日までは残り約2か月半あります。
ある程度覚悟していたものの、今回は長女の面倒を見る必要があり、第一子のときの状況と大きく異なります。
しかも、長女はイヤイヤ期に突入中(笑)
さて、どうしたらよいものか。。。
幸い、妻は即入院を要するほど酷くはなく、自宅安静を言い渡されました。
とはいえ、「悪化するようであれば入院だからね」と医師から言われている状況です。
切迫早産の対処法は、とにもかくにも横になって安静にすること。
医師からも、極力動かず横になっているようにと指示がありました。
また、腹圧がかかることはNG。
上記の対策をどうするか、妻と話し合いました。
妻の仕事をセーブ
妻は切迫早産により職場に行ける状況ではないため、産休までの大半は有給休暇を使い、日中、極力自宅で横たわって過ごすことにしました。
業務の引継ぎでどうしても出勤せざるを得ない日は、短時間出勤する形でしのぎました。
妻の職場は、産休の事例が多く、同僚の中にも出産経験者がいたため、理解を示してくれて大変助かったとのことです。
家事・育児分担の見直し
まず、はじめに見直したのが長女の保育園送迎。
こちらは、切迫早産の妻にとって負担が大きい育児タスクです。
保育園までは少し距離が離れているので、歩いていくのは負担が大きく、かといって自転車を使うのもバランスが不安定な上に子供を抱き上げるため腹圧がかかります。
さらに、前の記事でも書きましたが、イヤイヤ期の長女がすんなり帰ることは稀で、時間がかかることが目に見えています。
そこで、長女の保育園送迎を妻以外が担当することにしました。
私は出勤時間の関係で、朝送ることが出来ないため、近くに住む義父母にお願いし長女を送ってもらうことにしました。
帰りのお迎えは、定時帰りの私が行うことに。
イベントなどで、どうしても仕事が遅くなる時には、こちらも義父母にお迎えをお願いしました。
そしてその他の家事も、できる限り私が行うようにし、妻の安静時間を増やすようにしました。
長女の反応
妻は家にいるものの、基本的に横になっていて、今までのように構ってもらえない状況に、長女ははじめは不満だったようです。
そんな長女に、理解できる言葉で丁寧に説明し、「ママと赤ちゃんが元気でいられるように、助けてあげようね」と都度伝えるようにしていると、お姉ちゃんとしての意識が芽生えた様子です。
それからは「ママ、大丈夫?」と妻に声を掛けたり、いろいろと手伝ってくれたりするようになりました。
3歳の子供でも丁寧に説明することで、家族の一員として戦力になってくれました。
ストックした夫の有給休暇を使う
切迫早産の状態が続くと、たとえ安静にしたとしても、突然破水する可能性があります。
この時、妻が自力で病院へ行くのは難しく、連れていける人がそばにいないと、大変な状況に陥ることも考えられます。
このような時に、夫の有給休暇のストックが大きな効果を発揮します。
当時の私の場合は、前年からの繰り越しも含め約30日分の有給休暇が残っていましたので、このような時に備えてストックしておいて助かりました。
幸い、切迫早産中に破水することはありませんでしたが、妻の体調に合わせてスポットで有給休暇を使い、妻のサポートを行うことができました。
このように、私の場合はストックしておいた有給休暇が使えたおかげもあり、難を乗り切ることができましたが、このストックがなければ大変な思いをしていたかもしれません。
社会資源の活用も検討
一方、妻のほうでは、万が一、一人の時に陣痛がきたときに備え陣痛タクシーに登録していました。
陣痛タクシーとは、妊婦が事前に自宅や産院などの情報を登録しておき、陣痛が来た時に産院まで送ってもらうサービスです。
家族がサポートできない時に備えて、陣痛タクシーのような社会資源の活用も検討しておくと、対応の幅が広がり、安心ですね。
育休制度について思うところ
私たち共働き夫婦にとって、育休制度は大変ありがたいものでした。
欲を言えば、もう少し痒い所に手が届くところがあれば、と思うことがありましたので、下記に綴りたいと思います。
妻の緊急時に夫がスムーズに対応できる制度を
私たちに限らず、切迫早産などの状況で、妻が自力で病院へ行くのは難しくなる人も多数いるのではないでしょうか。
そうなると、夫の出番となりますが、2017年現在、男性の育休は子の出産後にしか適用されず、法的には男性の産休的な休暇はありません。
そこで、一部の会社は育児休業とは別に育児休暇制度というものを設けています。育児休業と育児休暇の違いについて知りたい方は、よかったら私が執筆しているこちらのコラムもご覧ください。
育児休暇が充実している会社であれば、不測の事態に備えて計画が立てやすかったのですが、当時の私の職場にはそのような制度がありませんでした。
妻をサポートするための夫の産前休暇を
妻のための男性の産前休暇は、国の制度や私の職場の制度にはなかったため、男性の産前休暇は有給休暇を使うしか手立てがありませんでした。
2022年の育児・介護休業法の改正により、「男性の産休」と言われている産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されたり、育児休業の分割取得が認められたりするなど、男性育休取得の促進に向けて年々改善されており、これはこれで喜ばしいことです。
しかし、育休取得者からの本音を言わせていただくと、産後パパ育休よりも産前パパ育休に力を入れてほしいと思っています。
実際、公務員には夫のための特別休暇として、配偶者出産制度というものがあります。
これは、妻の出産時に夫が付き添うことを目的とした休暇で2日間取得できます。
他にも、前述の切迫早産などの出産前トラブルなどに対応できる”ママケア休業”とかあると便利なのではないでしょうか。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
次回は、いよいよ第二子の誕生時のことをご紹介します。
なお、本記事を執筆したキャリアリカバーでは、男性育休6か月の経験を持つ国家資格キャリアコンサルタントが、仕事と家庭の両立、育休とキャリア形成、メンタルケアとキャリア形成などでお困りの方を対象としたキャリアカウンセリングをお受けしています。
関心のある方は、「人生が好転、自信がつくキャリアカウンセリング」のホームページもご覧ください。