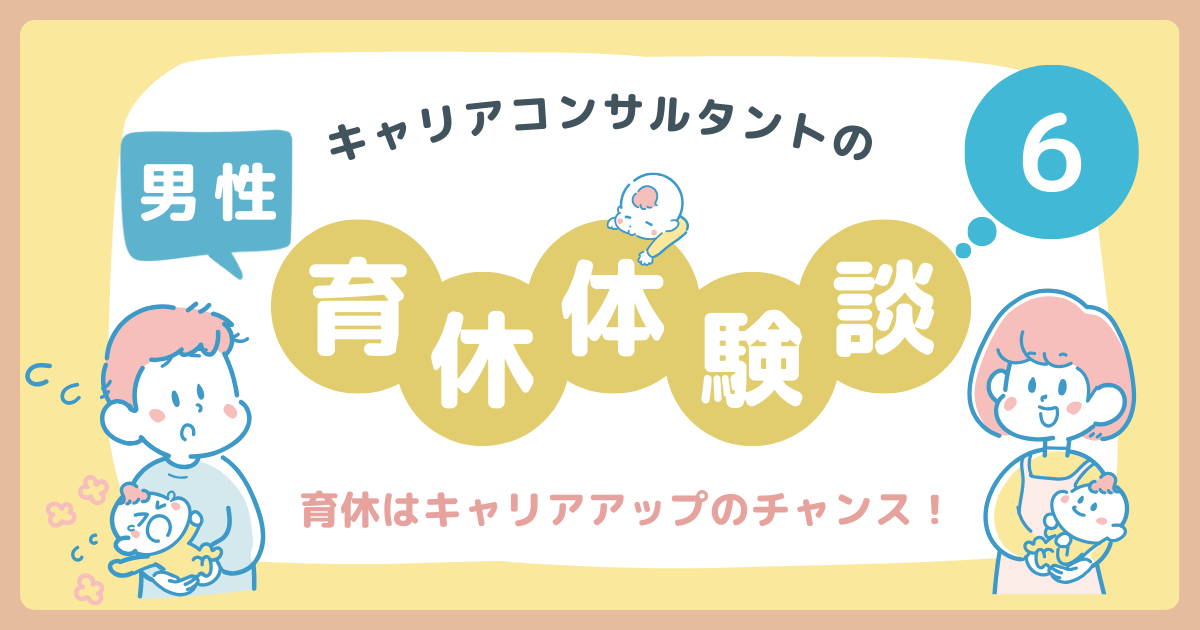前回の記事では、育休申出のタイミングと留意点についてご紹介しました。
男性育休取得の前例のない職場で育休取得を申し出、職場から受理され、無事に育休取得への道が開けた。。。
と思いきや、これですべてが終わったわけではありません。
ようやく「後ろめたい」モードから脱出し、安心したのも束の間、私にとって新たな試練が待っていました。
それは、育休開始日まで職場でどう過ごすか。
特に育休取得期間が長期にわたる場合、否定的な印象を持っている方も一定数いるため、居心地が悪くなることも考えられます。
しかも、今回の私のケースは、育休取得申出後に別の職場に異動となったため、より肩身の狭い思いをすることが予想されます。
今回は、育休取得申出後から育休開始日までの5ヶ月間、職場での人間関係悪化を回避するために、職場で意識したことや取り組んだことを綴ります。
育休申請後は全力で職場をサポート
職場の雰囲気や文化の理解を考えながら立ち回る
新しい職場に転勤したのは、第二子の出産予定日から遡って7月。
同年12月から6か月の育休に入るため、新しい職場での在籍期間は5ヶ月となります。
この限られた期間で、職場にどのように貢献できそうかを考えました。
異動後の業務内容は、異動前の業務とほぼ同様の内容でしたが、仕事に対する考え方や流儀、雰囲気が異なっていました。
そのため、「前の職場ではこんなやり方だった!」など、異動前の職場の文化を持ち出すと、雰囲気が悪くなるだろうと感じていました。
「郷に入っては郷に従え」の考え方は、転職7回での失敗を通じてイヤというほど学習しています。
数ヶ月後には6か月もの間不在になるわけで、上司や同僚にとって私は少なくとも歓迎ムードではないだろうと捉え、ここは出過ぎず、かといって萎縮しすぎず、慎重に行動しようと考えました。
業務内容を聞く過程で、仕事上の問題や悩みを聴く
そこで、まずは同じ部署の職員を知るために、業務内容を教えてもらう体で、話を聞くことに徹しました。
すると、その過程の中で、一部の職員が仕事への悩みや愚痴を語ってくれました。
このことがきっかけで、私の役割が一つ決まりました。
その役割とは、「部署内プチキャリアコンサルタント」笑
日が経つにつれプチ相談件数も増加、相談内容が重い場合は、別室で話を聴いたこともありました。
周辺業務に専念し後方支援する
「聞く」と「聴く」の姿勢を持ち続けることで、一部の職員とは相互理解を深め、関係性を築くことができました。
その単純作業も歓迎するという私の意向を伝えたところ、恐縮しながらも単純作業の依頼が寄せられました。
立場上、上司の補佐的にあたりますが、どのような単純作業であっても、全力で取り組むことに。
このように、適度に距離を保ちつつ、必要とされた時には全力で助言や業務を提供するというスタンスを維持しました。
私自身の力不足から、全ての職員と良好な関係を築くことは叶いませんでしたが、それでも一部の職員のモチベーション向上に寄与できたと感じています。
引継ぎや休職の連絡をする
引継ぎのスケジュールを立てる
育休開始日の2か月前には、担当業務を引き継ぐため、引継ぎのスケジュールを立てました。
引継ぎに関するノウハウは、こちらのコラムでもご紹介していますので、よかったらあわせてご覧ください。
育休取得による休職を全員に一斉メール
私は育休開始日の3週間くらい前に、育休取得により休職することを、全職員に一斉メールしました。
育休開始2週間前から有給休暇で休みをとったので、実質休みに入る1週間前になります。(その詳細は次回お伝えしますね。)
一斉メールした理由は下記の3つです。
一斉メールした理由3つ
- 復職後も職場と円滑な関係を築きたかった
復職後に自分が他部署の方と仕事をする場合や、将来的に他部署に異動になった場合、その部署に「育休のことを知らされなかった」という方がいると、気まずくなる可能性があります。 - 育休取得に否定的な方の誤解を解きたかった
特に管理職世代の方は、世代間のギャップから有給休暇の取得はおろか、男性の長期育児休業取得への理解は乏しいものと実感しています。
そのため、育児休業制度が法律上義務化されているとはいえ、育休取得に否定的な管理職世代や育休取得の機会を得られなかった他の方々にとっても、自身の育休取得について好ましく思っていない方もいるのではないかと推察していました。 - 男性育休の意義や重要性を全員に啓蒙したかった
育休取得当時、私の在籍していた職場では、男性の長期育休の事例がありませんでした。
今回の育休取得をきっかけに、将来育休取得を検討されている男性職員がスムーズに取得できる環境づくりのきっかけになるチャンスと思ったのです。
一斉メールの送付内容
とはいうものの、実際にどのようなメールを送付してよいか、私なりに結構考えました。
色々とシミュレーションした結果、下記の内容でメールを送信しました。
- 育休を取得する期間と復職の日
- 育休の取得により、自部署の方はもちろんのこと、他部署の方々にも迷惑をかけてしまうこと
- 育休取得にあたり理解していただいたみなさんへの感謝
- 本来一人ひとりに挨拶すべきところ、一斉メールでの連絡になってしまうことへのお詫び
メールって後戻りできないですからね。
しかも全職員一斉。
果たして、どのような反応があるのか。
肯定的な反応か、それとも否定的な反応か。。。
メールの文面を何度も見直します。
そして、いよいよ送信!
このとき、メールの送信ボタンが一瞬何かの発射ボタンに見えました(笑)
一斉メールしたら思いもよらぬ反応が。
なにせトップを含む全職員へのメールですから、やはり反応が気になるところ。
さて、結果は。。。
一部の管理職の方からは、全員に育休取得のメールを送付するのは不適切ではとの反応がありましたが、メールの返信のあった方の大半は、好意的な内容でした。
トップの方をはじめ、普段あまり接することがない方からも励ましのメールが届いており、大変うれしい気持ちになりました。
また、このメールのやりとりをきっかけに、関係が深まった方もいらっしゃいます。
すでに育休を取得された女性の職員からは、育児のポイントを教えてくださったり、不要となった幼児グッズを差し上げたいとの申し出もありました。
さらに、驚いたことに、このメールが実は思わぬ結果をもたらすことになりました。
私の当時の職場は大学でしたので、職員の他に全教員にも育休取得メールを送付しました。
すると、意外な反応がありました。
それは、「育児休業から復帰したら、男性育休のテーマで学生に講演してほしい」というもの。しかも立て続けに2件。
後日談になりますが、復職後、実際の授業でこの講演を行ったところ、学生からの反応が好評で、その噂を聞きつけた他学科からも講演依頼があり、育休講演業務が増えることになりました(笑)
そして、大学を退職してから現在も、前職の大学をはじめ、様々なところで毎年講演を行うことに。
まさか、このような結果になるとは思ってもいませんでした。
人それぞれ受け止め方が違うので、すべての方に良い結果をもたらすのは難しいと思いますが、私自身としては、勇気を出して送付してよかったと思っています。
メールだけにとどまらず、可能な限り多くの職員に対面挨拶
アナログのコミュニケーションは重要
しかし、育休の連絡をメールだけで済ませてしまうのは、私の性格的に違和感がありました。
そこで、育休取得前の最終出勤日やその前日までには、可能な限り多くの職員に対面による挨拶をしようと考えました。
私の考える挨拶のきっかけになる有用アイテム、そう、それは菓子折りです。
さすがに全職員分用意するのは無理がありましたので、同じ敷地内の関係部署と異動前に長年お世話になった職場のみなさんに渡すことにしました。
菓子折りは、部署ごとに1セット購入し部署の上長に渡す、という手段ではなく、一人ひとりに手渡しができるよう、個包装のお菓子を選びました。
なぜその方法を選んだかと言うと、お菓子の手渡しを通して、一人ひとりに感謝の意を伝えることが大事だと思ったからです。
男性育休への理解は、少しずつ浸透されつつありますが、まだまだ大半の会社が歓迎的ではないと思います。
そのため、申し訳ない気持ちや気まずさが先立ち、批判を浴びたくない気持ちから、メールだけの挨拶で終わってしまいがちです。
しかし、その方法では気まずい気持ちのまま育休に入ることになり、そのような気持ちを抱いたまま職場復帰するのは避けたいと思いました。
そこで、育休に入る前にお互いの気まずい(であろう)気持ちが和らぐことを期待して、菓子折り持参による対面の挨拶を選択した次第です。
事前に育休メールを送付していましたので、いきなり感もなく、自然に挨拶することができました。
すると、育休取得に好意的でないであろう一部の方の反応は、それまでの固い表情から柔らかい表情に。
この対面による挨拶では、直接批判を浴びたことはありませんでした。(心の中で批判をされたことはあったかもしれません。)
もしかして、選んだお菓子がよかった?(笑)
育休直前、またもや人事異動が発令
さて、そんな私ですが、休みに入る数日前に上長に呼ばれ会議室に。
「育休復帰後は、別の部署に異動してほしい。」
・・・・・・えっ!?(笑)
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。次回に続きます。
なお、本記事を執筆したキャリアリカバーでは、男性育休6か月の経験を持つ国家資格キャリアコンサルタントが、仕事と家庭の両立、育休とキャリア形成、メンタルケアとキャリア形成などでお困りの方を対象としたキャリアカウンセリングをお受けしています。
関心のある方は、「人生が好転、自信がつくキャリアカウンセリング」のホームページもご覧ください。