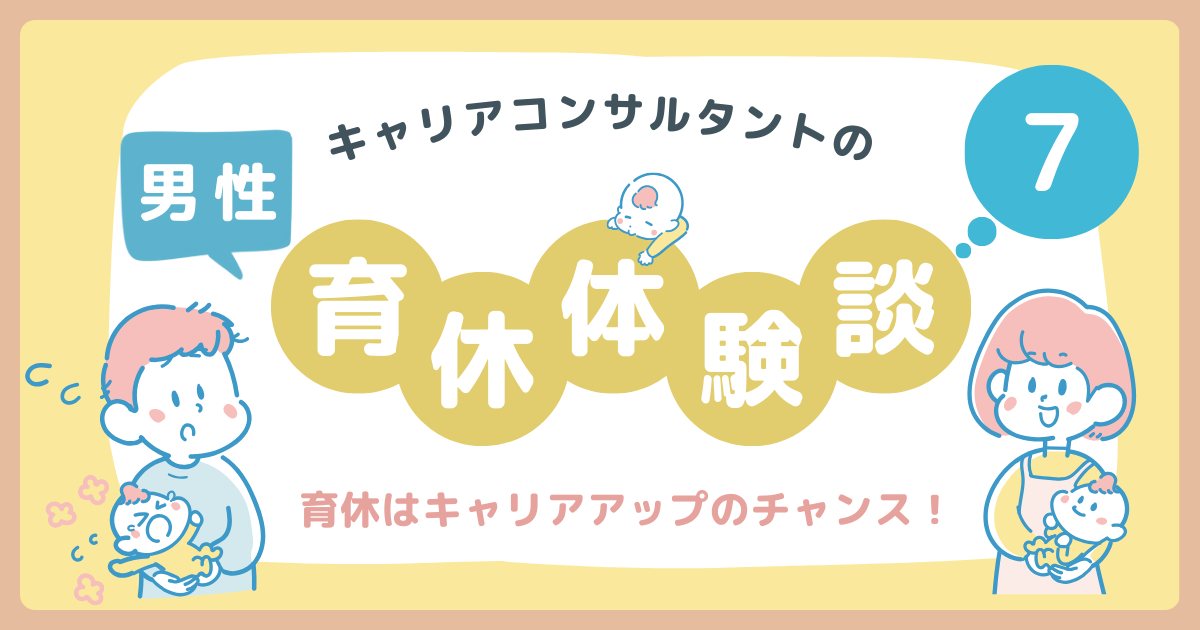前回の体験談では、育休開始前までの職場での過ごし方について、体験談と留意ポイントをご紹介しました。
今回は、家庭に視点を切り替えて、育休開始までの家族生活の実際についてご紹介します。
第二子妊娠前の共働き家庭の家事・育児分担
第二子妊娠時の家庭生活をお話する前に、それまでの共働きの我が家の家事育児分担について、お伝えしたいと思います。
家事の役割分担
家事の仕事をざっくり分けると料理、洗濯、掃除に分けられると思います。
料理について妻と夫の私のタイプを挙げると、妻は時間をかけて丁寧に仕上げるタイプで、料理自体があまり好きではありません。
一方、夫の私は冷蔵庫の品を適当に組み合わせて早く仕上げるタイプで、雑ではありますが笑、料理が苦ではありません。
そのため、夫の私が主に料理を担当することになりました。
ただし、朝食に関しては夫は出勤時間が早めで、朝食を摂らなかったり、適当に一人で済ませることもあったため、夫の分以外の朝食は妻が担当していました。
洗濯は妻が担当。
私の洗濯技術は、妻が洗い直したがるほどの低いレベルのため、残念ながら妻の及第点には達しませんでした。
私もきっぱり認めています(笑)
掃除は、長女も交えて随時気付いた人が行っていました。
次女が妊娠した際の長女は2歳でしたが、ゴミ捨てや何かを取ってくるなど、戦力になってくれてます。
お願いしてありがとうと感謝の気持ちを述べるとまんざらでもない顔をしているので、つい、また頼みたくなってしまいます。
育児の役割分担
育児に関しては、長女の身の回りの世話全般(朝の支度や寝かしつけ等)、保育園の送迎は主に妻が担当。
妻が仕事などの用事のある場合は、夫の私が担当します。
ただし入浴は、長女の指名により、夫婦のどちらかが一緒に入浴するというシステムです(笑)
指名を受けられないと、なんとなく寂しくなります。
外遊びに関しては、ちょっとした近場の公園等は妻が付き添うことが多く、休日に家族で遠出する際は、夫が計画してドライブするといった具合。
夫婦それぞれの得意分野を活かした家事育児分担になっているかと思います。
妊娠初期の家庭生活
妊娠初期の家事・育児
妊娠初期は、夫の私が育休取得を最終決定していない時期でもあり、また、長女に妊娠を隠している時期でもあるので、基本的には家事分担や長女の対応は妊娠前と変えずに行っていました。
ちなみに、長女に妊娠を隠していたのは、妻が高齢出産ということもあり、安定期に入るまでは長女経由で不特定多数の人たちに伝えたくない意向があったからです。
長女に伝えたら最後、保育園で園児や先生を見かけては、「あのね、わたし、もうすぐ妹ができるんだよ」と、スクープのごとく話しまくるのが容易に想像できましたから・・・(笑)
妻のつわりは幸い比較的軽く済んだため、生活に大きな影響を及ぼすことはありませんでした。
それでも体調的に厳しいときもあり、その時は夫が妻の家事を多めに担当しました。
夫の育休についての話し合い
この時期、私たちは夫の育休についてじっくり話し合いました。
話し合いでは、出産後の夫婦生活をイメージしながら、下記のポイントについて検討しました。
- 育休開始時期:いつから育休を取るのか
- 育休期間: どのくらいの期間、育休を取得するのか
- 復職後のキャリア形成: 育休明けの仕事との両立やキャリアの進め方
詳細について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
特に前例のない職場での育休取得希望を伝えるにあたって、どのようなタイミングでどのように伝えたらよい反応を示してもらえるかのシミュレーションをおこないました。
この時期にしっかりと戦略を立てることで、出産後の生活がスムーズに進むように準備しました。
妊娠中期の家庭生活
長女に妊娠を伝える
安定期に入った妊娠中期のタイミングで、当時3歳の長女に「もう少ししたら妹ができるかもしれないよ」と伝えました。
実際、長女は妹ができると知ると、嬉しくてしかたなかったようです。
そして気が付くと、保育園の先生全員が妻の妊娠を知っている状態。案の定周りに言って回っていたのでしょう・・・予想的中(笑)
出産時までの課題や役割分担についての話し合い
安定期に入った妊娠中期には、職場で育休取得が受理されたことも踏まえ、出産時までの課題や役割分担などについて家族で話し合いました。
長女に妹の誕生を伝えてからは、長女にも家族会議に参加してもらいました。
長女は、これから妹ができることは理解していましたが、家族の今後の生活の在り方については、ピンときていなかったと思います。
しかし、長女に関係することについては、長女を交えて話し合っておきました。
「何かを決めるときは、一方的に決めるのではなく、家族の話し合いを経て決めることが大切」
ということを長女に実感してもらい、家族の一員である自覚を持ってもらいたい、という想いがあったからです。
例えば、ゴミ捨てなどの家事分担などについて、子どもを交えて話し合っておくと、子どものモチベーションが上がったり、協力的になったりします。
これも過去にパートナーに相談することなく一方的に物事を決めたことでパートナーに振られた失敗経験の賜物です(笑)
話し合いの内容と結果
話し合いの内容は以下の通りです。
■ 家事・育児はどうするか
妊娠前の役割分担を基本とし、重労働な作業やバランスを崩しやすく転倒の恐れがある作業は夫が担当するようにしました。
■ 長女の面倒はどうするか
中期初めのうちは、こちらも妊娠前と同様の役割分担。
ただし、途中からは夫の役割を増やしました。それは後述します。
■ 出産時はどうするか(産院・入院時)
第一子の時、妻は里帰り出産しました。
第二子の今回は、長女がいて保育園に通っている状況であること、また、第一子出産後に妻の実家近くに引越したことにより、容易に妻の両親から支援を受けられる状況であることから、里帰りはしないことにしました。
産院は、妻が絶賛していた第一子を出産した病院を選択。
出産時は夫が休みをとり立ち合い出産することにし、その際に長女の面倒を見る必要がある場合は、妻の両親にお願いすることにしました。
■ 切迫早産の可能性への対策
第一子である長女の妊娠時、妻は切迫早産となりました。
その際、産婦人科の先生より切迫早産になりやすい体質だから、第二子以降も気を付けたほうが良いとのアドバイスをもらっていました。
切迫早産とは、早産の一歩手前の状態になることで、治療は第一に安静にすることです。
そのため、もし第二子でも切迫早産になると、長女の面倒をみることは難しくなることが想定されます。
そうなったら、夫が対応できるのが好ましいというのが家族の総意でした。そこで、出産前にも休みが取れるよう有給休暇をストック、早めに職場の上司にもその状況を伝えておきました。
長女のイヤイヤ期と育児の工夫
長女のイヤイヤ期と妻の疲弊がピークに
この頃は長女のイヤイヤ期がピークに差し掛かっていました。
イヤイヤ期は、一般的に早くて1歳半から始まり、2歳頃にピークを迎えると言われていますが、私の長女は3歳がピークでした。
身重の妻にとって、イヤイヤ期の娘の対応は負担が大きく、お腹が大きくなる頃には疲労がピークになっているように感じられました。
もしかすると、下の子が妊娠したことにより、上の子である長女が母親と関わる時間が少なくなることを心配したのかもしれませんね。
いずれにしても、この状況が続いてしまうと、妻のストレスが増大するのはもちろんのこと、生まれてくる下の子にも何らかの影響が出る恐れがあります。
そこで、夫である私が「イヤイヤ期対応係」を拝命(笑)、ぐずり&かまってモードに突入した長女を相手することにしました。
特に印象的だったのは、保育園帰り。
保育園から家に帰りたがろうとせずに公園で遊びたいと主張し、地蔵のように動かず・・・
どのような言葉を伝えても効き目がなく、途方に暮れていたところ、たまたま勤務終了後に通りかかった保育士の先生の一言で、地蔵モードが解放されたときには、先生が神に見えました。
しかし、神は毎日都合よく降臨せず、神に出会えない日は、地蔵に語りかけてはイヤイヤの繰り返し。
長い時には1時間近くも交渉したこともあります。
営業やキャリアカウンセリングの仕事をかれこれ25年近く経験してきましたが、これほどコミュニケーション力を鍛えられたのは、地蔵娘のほかに思い浮かびません(笑)
イヤイヤ期対応もキャリアアップ
イヤイヤ期は、子どもの成長過程において、自己主張が強くなる発達段階の大切な時期。
そして、子どものイヤイヤに対して叱り付けると逆効果になることは理解はしていました。
しかし、理論的には理解しつつも、実際に子どもと対峙すると、そううまくいかないものです・・・。
この状況を脱出するためのこれといった正解は見つかりませんでしたが、比較的効果があったのは、見守りながら子どもの置かれている状況を子どもに伝えることでした。
「ここにいたいのかなー」とか「帰りたくないんだねー」とか「公園に行きたいのかなー」など、子どもの行動そのものに対して声をかけながら子どもを見守るよう心掛けました。
すると、たまに「おうちに帰りたい」と言い出して、すんなり一緒に帰ってくれたことも!
仕事帰りで夕飯の支度をしたい親としては、子どもを一刻も早く家に帰したいと思うことが多いでしょう。
一方、子どもにとってみれば、保育園での遊びの余韻があるのか、すぐには家に帰らずもっと外で遊んでいたい、という思いを持っていることが多かったです。
そのような時に、自分の課題を子どもに無理やり押し付けず、自分の課題を一旦脇において子どもの課題に寄り添ったことが、いま思えば効果的だったような気がしています。
このイヤイヤ期対応業務の経験は、後の様々な仕事や育児などに大変役立ったのを実感しています。
長女よ、あの時はぐずってくれてありがとう(笑)
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。
次回に続きます。
なお、本記事を執筆したキャリアリカバーでは、男性育休6か月の経験を持つ国家資格キャリアコンサルタントが、仕事と家庭の両立、育休とキャリア形成、メンタルケアとキャリア形成などでお困りの方を対象としたキャリアカウンセリングをお受けしています。
関心のある方は、「人生が好転、自信がつくキャリアカウンセリング」のホームページもご覧ください。